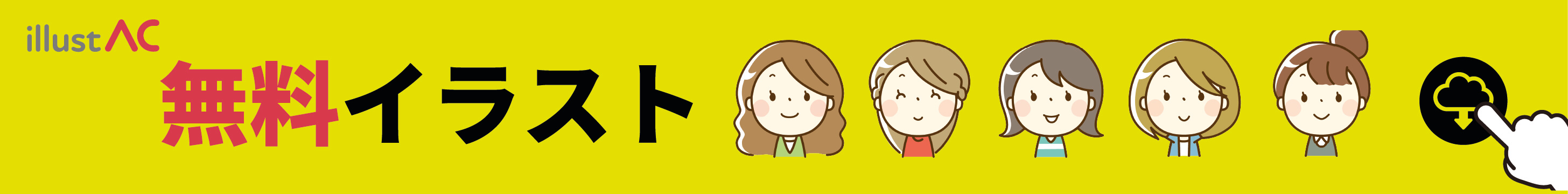帯で絵画を表現
テレビで、国宝「那智瀧図」を帯に織りあげるドキュメンタリーを観ました。
NHKBSプレミアム・イッピンスペシャル『究極の帯・山口源兵衛と仲間たち』です。

その絵は、鎌倉時代に描かれたもので作者不詳、現在、根津美術館に所蔵されています。
誰が何のために描いたかは分からないのですが、当時から那智の滝は熊野三社のご神体=飛瀧権現として信仰の対象になっていて、時の亀山上皇が御所に居ながらお参りができるよう描かれたのではないかと推測されているようです。
この絵の神々しさを帯で表現するのが30年来の願いだったという源兵衛さん。
源兵衛さんは280年続く西陣の帯問屋さん。
これまでにも、一流の職人を集め、伊藤若冲などを帯にして、絵画の複雑な色使いを、太い糸、細い糸、金銀箔の糸などを組み合わせて帯に織りあげてきました。
そして、いよいよ長年の願いを実行に移したのです。
それまでに源兵衛さんの難しい注文に応えてきた染色家、金糸銀糸の製作者、絵の通りに帯を織りあげるための設計図である紋図作成者の試行錯誤が始まります。
シルクの染色は奄美大島の伝統的な泥染めを採用、西陣の枠にこだわりません。

途中、ずっと一緒に仕事をしてきた織り師が参加を断り、西陣では織り師を見つけられなくなりました。
そこで、「もうあの子しかいない」と最後の頼みの綱となったのは、24才の奄美大島の女性織り師でした。
試し織りの作品がいくつも奄美から京都に送られ、その度に糸や紋図を作り直し、それでもうまくいかず本物の那智の滝を見に行ったりもします。
織り師の呼吸が乱れただけで帯に筋が入ってしまうのです(*_*;
織っている途中でも、糸の組み合わせによって、大事な色が裏に隠れて目立たなくなることもあり、そうなると、ほどいて、設計図からやり直しです。
最後の仕上げは徹夜、京都から駆けつけ待ち構える源兵衛さんが仕上がりを見て、「よう頑張ったな」と一言。
織り師の目にはにじむものがありました。
う~ん・・・・負けました💦
実は、私は最初、帯はあくまでも・・・
締めてこそと思っていました

帯はお太鼓にした時に一番きれいに見えることを前提に織ってあります。
後は、結んだときに半分に折って前に出るところ、それからお太鼓結びの下からのぞくタレの部分に焦点が合わされています。
全体に図柄を織り上げてあって、お太鼓以外の結び方に合う場合も、背中に結ばれた時が大事なのは同じです。
これは、帯が結ばれてこそ完成だからです。
それなのに、絵画表現を織物でどこまで真似られるかなんて、帯道(?)から外れてるとしか思えませんでした。
そう思いながらもテレビを切らなかったのは、私の二大趣味といっていい、美しい布と人の生き方が次々に紹介されていき、目が離せなかったからです。
彼らが挑戦していたもの
彼ら、源兵衛さんと一流の職人さんたちの異様さから目が離せなくなりました。
まず、中心の源兵衛さん、骨格のしっかりした体に、丸坊主、粋な和服姿がいかにも京の旦那衆といった感じです。
280年も続く老舗の旦那さんですから、それはもう、京の旦那の代表ですよね。

〈閑話休題〉そういえば、私にも親戚にマイナーめの京の旦那がいました。
母の妹の嫁いだのが京都は寺町の菓子屋の次男だったのです。
叔父は、本家の社員として毎日出勤していたようです。
「男はんは、しょうないな」というのが叔母の口癖でしたっけ。
「男性は仕方ない」、つまり、男性のしょうがない習慣的生活態度への忍従ともあきらめともいえる、母性的な言い逃れ(-_-;)
子供のころは夏休みなどよく遊びにいっていましたが、叔母は夜更け(朝方?)に帰る叔父を寝ずに待っていたようです。
帰ってきた時、お茶漬けを出したりしないとなりませんからね。
叔父が死の床で叔母の手をとり、「苦労かけたな、堪忍してや。おおきに。」と言ったので、叔母の恨みは一瞬で霧散し涙がこぼれたそうです。
叔父も叔母も他界した今、モダンな京都では旦那衆の生活習慣もだいぶ違うことでしょう。
この余談は源兵衛さんのことではありませんので、お間違えありませんよう(笑)

源兵衛さんの挑戦を、大店の旦那の贅沢な遊びくらいにしか思えずに見始めた私ですが、やがて、源兵衛さんの「本気」に圧倒され、職人たちの差し出す試作品をにべもなく却下する否定語の裏に、本物を感じてる人の自信が見えてきました。
源兵衛さんは、西陣織に表現できない絵はないと信じ、那智瀧図の神々しさの表現に挑戦しているのです。
これは、源兵衛さんが那智瀧図から神々しいと名付けられるエネルギーを感じ取っているからこそ生まれる発想です。
見えないけれど感じる物を、見えるもので表現するのは、職人さんの仕事です。
一見普通のおじさんにしか見えない職人さんたちですが、中身は全身職人さんなのです。
頼まれた仕事のことしか考えていなくて、思いついたら黙々と試作する。
やり直しとなったら、また黙々とくりかえすだけ。
この姿、実は多くの職業人に共通のことですよね。
しかし、私が異様に感じたのは、注文主の要求が明確に了解できなくても、黙々とやり続けるという点です。
源兵衛さんが感じて表現しようとしている「神々しさ」は、お互いに確認できない、個別的で不確かな物にもかかわらず作り続けるのです。
ここにあるのは、限界を超えることへの挑戦。
昔、登山家がなぜ山に登るのか尋ねられて、「そこに山があるから」と答えていましたが、それを思い出します。
進むべき道に壁が立ちはだかっていることに気づいたら最後、超える以外に道はありません。
帯『那智瀧図』完成
出来上がったものは、絵のマネではありませんでした。
元の絵とは全く別の、独自の輝き、神々しさを放つ織り物芸術作品でした。
私には帯である必要もなく、一幅の掛け軸のようにも見えます。
西陣織の表現の可能性は、確かに証明されました。
しかし、もう一つ忘れてならない条件は、帯であることです。
織物の可能性に挑戦するだけなら、タピストリーでも、掛け軸でもいいはずです。
しかし、源兵衛さんの夢は、国宝『那智瀧図』の神々しさを西陣の技術で帯に表現することでした。
これは、源兵衛さんがたまたま帯屋さんだったからという意味にはとどまりません。
帯でなければならなかったのです。
帯とは何か
源兵衛さんは、店を継ぐときお母さんに言われた言葉を、今もかみしめています。
「帯とは、陰でじっと家族を支え、損ばかりしている女が、一世一代のおめかしをするときに締めるもの」
それなら、作る方も、一世一代の最高の技術と最高の材料で最高の輝きに挑戦するしかない、ということになります。
帯を締める女性の人生の悲喜こもごもを、丸ごとを受けとめ、包み、支えるのが帯なのかもしれません。
うーん、重いです。
なぜか、叔母が思われてなりません。

帯は背中で人に見せる物と思っていた私は、単純にすぎたかもしれません。
着物は下着から凝っているし、帯周りの小道具も念が入っています。
これって、見る人より、身に着ける本人の満足の方が大きいですよね。
帯の背は自分からは見えないけれど締めている自分の気持ちを引きたて、自己満足に近い喜びがあります。
羽織姿なら帯は見えないのに、帯を手抜きをする気にはなりません。
素晴らしい帯をきちんと締めることは、腰や背中を支えてくれるコルセットの役目も果たしながら、自信や誇りを手放さないよう心の支えにもなっている気がしてきました。
女性が帯を選ぶ時、実は、帯と自分自身とを天秤にかけています。
人生を背負って、今いるこの自分と、バランスの取れる帯、どちらかが重すぎても、軽すぎても安心して締めることはできません。
帯と女性の間にあるのは、人生をかけた真剣勝負の緊張感です。
女性は帯を選ぶ権利があります。
そして、帯には締める人を選ぶ風格(独自の輝き)があるのではないでしょうか。
その風格を醸し出しているのは、とりもなおさず、源兵衛さんたちのような作り手の美意識とそれを実現するための技に他なりません。
その美意識や技は作り手の人生全体から生まれるものです。
そう考えると、
帯の重さは、締める女性の人生の重量であると同時に、作り手の人生の重量でもあります。
帯とは、女性の人生を支える作り手の人生の象徴、と言うこともできますね。
もう使われなくなった帯で、バッグや小物を作っていますが、一本一本の帯としっかり向き合っていきたいと思います。
作品は minneで販売中です。